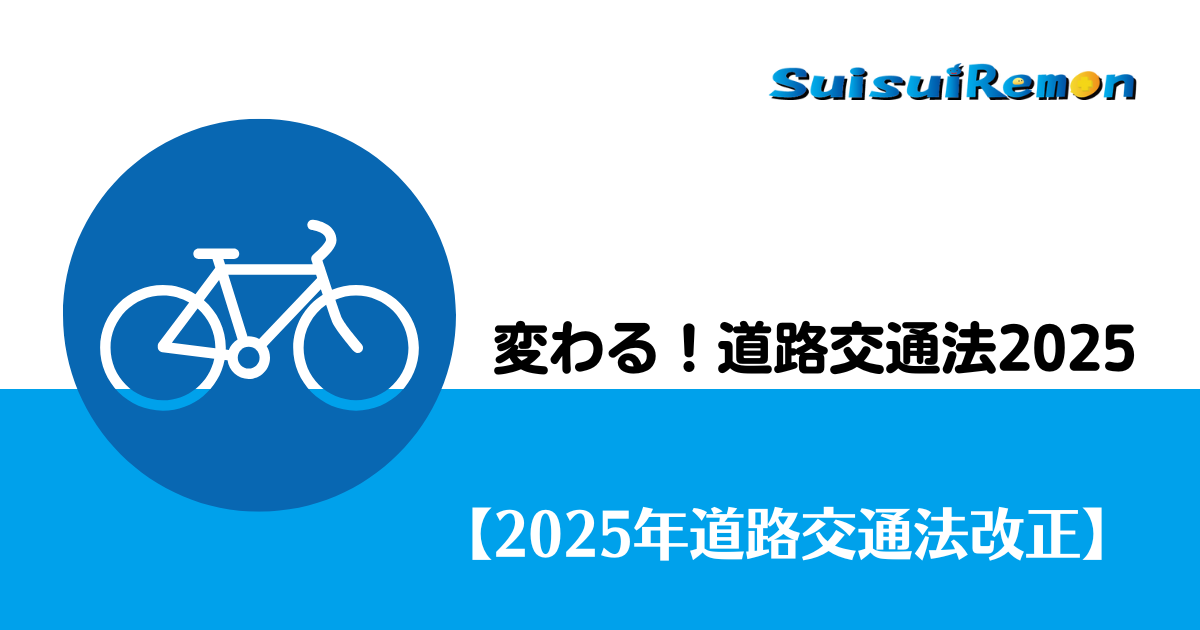【2025年道路交通法改正】訪問介護・訪問看護の自転車利用に何が変わる?
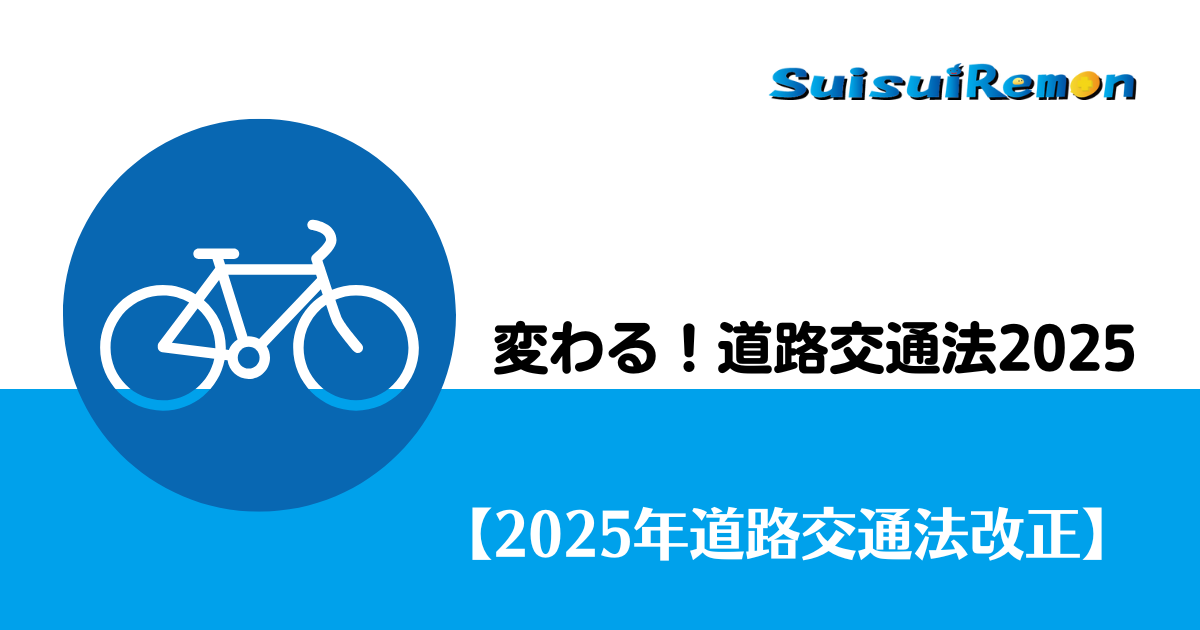
目次
現場で欠かせない「自転車」という移動手段
訪問介護や訪問看護では、利用者宅を短時間で巡回するために自転車や電動アシスト自転車が欠かせません。
特に都市部では渋滞を避け、時間どおりに訪問できる効率的な移動手段として多くの事業所が採用しています。
しかし2025年に施行される道路交通法の改正により、この日常的な「移動」が大きく変わる可能性があります。
法改正を正しく理解し、早めに対応を進めることが、安全な運営とリスク回避につながります。
2025年の道路交通法改正のポイント
今回の改正は、全国的に増加する自転車事故への対策として実施されます。
特に注目すべきは、次の3つのポイントです。
- ヘルメット着用の実質義務化
2023年の改正では「努力義務」でしたが、2025年4月以降は罰則を伴う義務化が段階的に導入される見込みです。
業務中に自転車を利用する職員も対象となります。 - スマートフォン操作・イヤホン運転の罰則強化
「ながら運転」はより厳格に取り締まられ、反則金や点数制度の対象となります。
訪問中の地図確認や電話対応の際には、特に注意が必要です。 - 事業者責任の明確化
業務として自転車を使用する場合、事故が起きれば管理者・経営者が安全配慮義務違反を問われるケースがあります。
事業所全体で安全管理体制を整えることが求められます。
訪問介護・訪問看護への影響
今回の法改正で影響が大きいのは、「個人の行動」だけでなく、事業所運営全体です。
- 職員のヘルメット着用を義務付ける必要がある
- 自転車の整備・点検の記録を管理しなければならない
- 事故発生時の対応マニュアルを整備しておく必要がある
- 損害賠償・労災保険の見直しが求められる
つまり、「自転車の安全利用」は、個人任せではなく組織的な管理課題に変わろうとしています。
法改正対応を怠るとどうなるか?
万が一、業務中に職員が事故を起こした場合、
- 罰則・反則金の支払い
- 損害賠償責任(人身事故の場合、数百万円単位)
- 行政指導・監査のリスク
といった影響が発生します。
また、SNSなどで「職員が無ヘルメットで訪問している」などの投稿が拡散されると、
事業所の信用失墜につながる可能性もあります。
利用者や家族にとって“安全で信頼できるサービス”であるためには、
法令遵守とリスク管理の徹底が欠かせません。
経営者が今から準備すべきこと
- 職員への周知と教育
法改正の内容をわかりやすく説明し、「なぜ必要なのか」を理解してもらう。 - 社内ルールの見直し
ヘルメット・反射材の着用、雨天時の対応、点検記録などをマニュアル化。 - 自転車保険・損害保険の加入確認
全職員が業務中もカバーされる保険体系を整備。 - 安全チェックリストの運用開始
点検・教育を月次で実施し、監査にも対応できる記録を残す。
まとめ:安全管理は“コスト”ではなく“信頼投資”
道路交通法の改正は、「取り締まり強化」だけを意味するものではありません。
それはむしろ、訪問介護・看護の現場が**“安全と信頼”を守る仕組みをつくるチャンス**でもあります。
安全対策を進めることで、
- 職員が安心して働ける
- 利用者・家族からの信頼が高まる
- 行政・自治体との関係が良好になる
といった好循環が生まれます。
今後、法改正はさらに続く見込みです。
早めの情報収集と社内整備で、リスクを「未然に防ぐ」経営を目指しましょう。