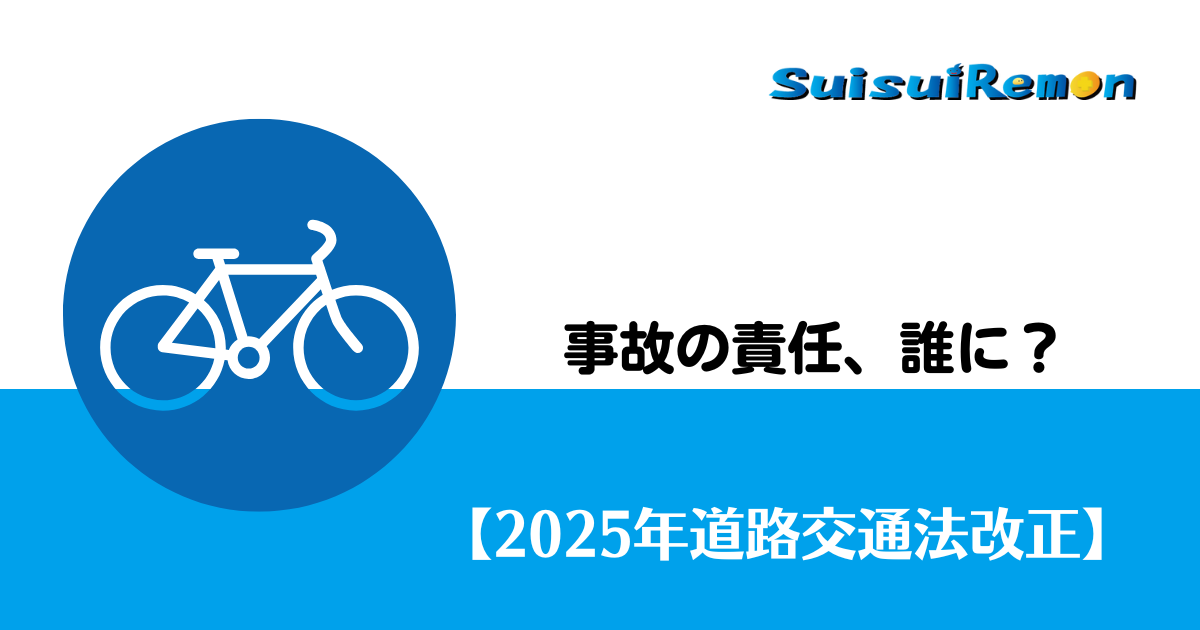【2025年道路交通法改正】訪問介護・訪問看護での自転車事故と事業者責任とは
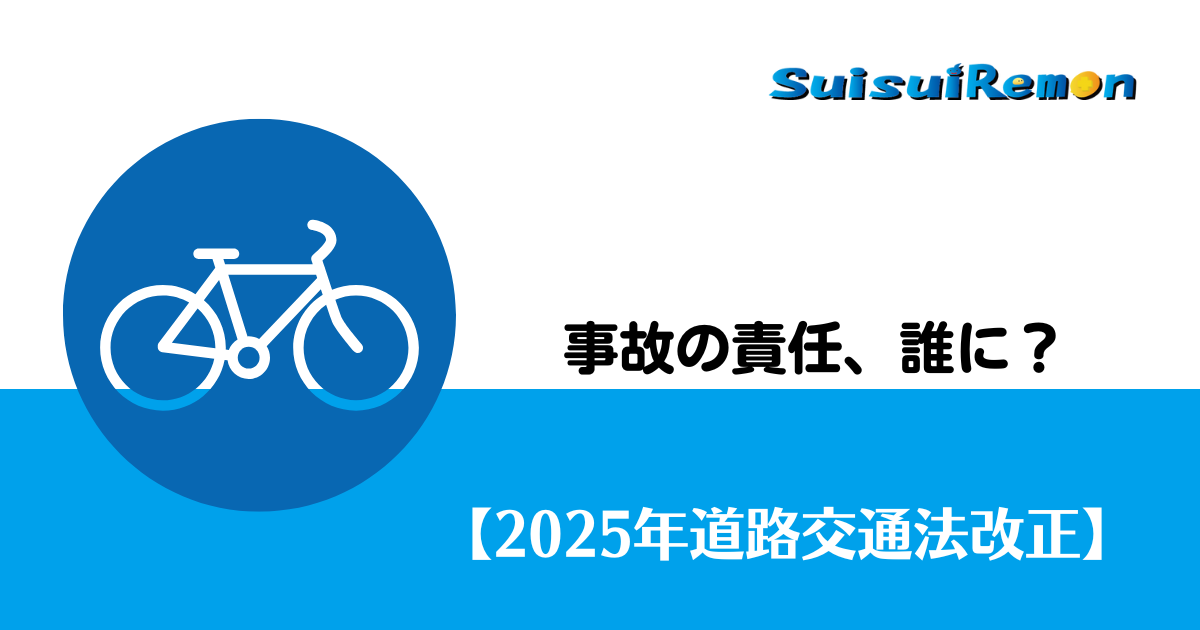
増加する自転車事故、介護・看護現場も例外ではない
訪問介護や訪問看護の現場では、短距離の移動が頻繁に発生します。
都市部では自転車を利用する職員が多く、効率的な移動手段として定着しています。
しかしその一方で、業務中の自転車事故が全国的に増加しています。
警察庁のデータでは、近年の自転車事故の約4割が業務や通勤中に発生しており、特に介護・医療職種での報告が増えています。
2025年の道路交通法改正により、こうした事故に対する罰則や責任の所在がより明確に問われるようになります。
罰則の強化と「業務中の事故」の扱い
2025年改正では、以下のような罰則強化が実施されます。
- ヘルメット未着用時の反則金制度(段階的導入)
- ながら運転(スマホ・イヤホン等)への厳罰化
- 酒気帯び・一時不停止など軽微違反への厳格対応
これらは「個人の運転行為」に対する罰則ですが、訪問介護・訪問看護のように業務で自転車を使う場合は話が異なります。
業務中に発生した事故は、**事業者にも「安全配慮義務違反」や「監督責任」**が及ぶ可能性があるのです。
つまり、事故を起こした本人だけでなく、
「ヘルメット着用や安全教育を徹底していなかった管理者」
「安全マニュアルを整備していなかった法人」
も、法的・社会的責任を問われるリスクがあります。
想定されるリスクと責任の範囲
1. 民事責任(損害賠償)
業務中に歩行者などを巻き込んだ場合、損害賠償金は数百万円〜数千万円にのぼるケースも。
自転車事故は「軽い接触」でも後遺障害が残ることがあり、賠償リスクは決して小さくありません。
2. 刑事責任(過失運転致傷)
過失の程度によっては、罰金・禁錮刑の対象となります。
「ながら運転」や「安全確認不足」が原因とされると、業務上過失として刑事事件化することもあります。
3. 行政責任・監査リスク
重大事故が発生すると、自治体や監督官庁による監査や指導が入る場合があります。
特に「安全管理体制の欠如」が指摘されれば、事業継続に影響する恐れも。
保険と労災の取り扱い
事故が発生した際の補償は、加入している保険の内容によって大きく異なります。
ここを誤解している事業所も少なくありません。
| 補償の種類 | 対応範囲 | 注意点 |
|---|---|---|
| 自転車保険 | 他人をケガさせた場合の損害賠償 | 加入義務がある自治体も多い。業務中も対象になる契約内容にする必要あり。 |
| 業務災害補償保険(労災上乗せ) | 職員自身がケガをした場合 | 通勤・業務移動を対象に含めること。 |
| 施設賠償責任保険 | 事業者が被害者から請求された場合 | 契約内容に「自転車業務中」を含める必要あり。 |
特に、業務とプライベートの区別が曖昧な訪問業務では、補償範囲の確認が重要です。
「勤務中の移動中だったか」「利用者宅訪問の前後だったか」で、保険の適用可否が変わることもあります。
経営者が行うべきリスク対策
経営者として最も重要なのは、「事故を防ぐ仕組み」と「発生後の対応体制」を整えることです。
1. 安全ルールの明文化
- ヘルメット・反射ベスト着用を義務化
- スマホ操作禁止・雨天時運転ルールなどを明記
- 点検・整備記録を職員と共有
2. 職員教育・研修の定期実施
- 年1回以上の「交通安全講習」を実施
- 新任者には必ず初回研修を設定
- 事故発生時の報告ルートを明示
3. 保険と契約の見直し
- 損害賠償責任保険、自転車保険、労災上乗せ保険の適用範囲を確認
- リース契約で貸与している自転車も対象に含める
信頼を守る“予防経営”がこれからの標準に
事故は、たった一度でも事業の信頼を揺るがします。
利用者や家族は、職員の安全意識が高い事業所を選ぶ傾向にあります。
「法令を守る」だけでなく、「安全を守る文化」をつくることが、これからの介護・看護経営に求められる姿勢です。
法改正を契機に、自転車の運用ルールを改めて見直し、
“安全=ブランド価値”として発信できる事業所を目指しましょう。