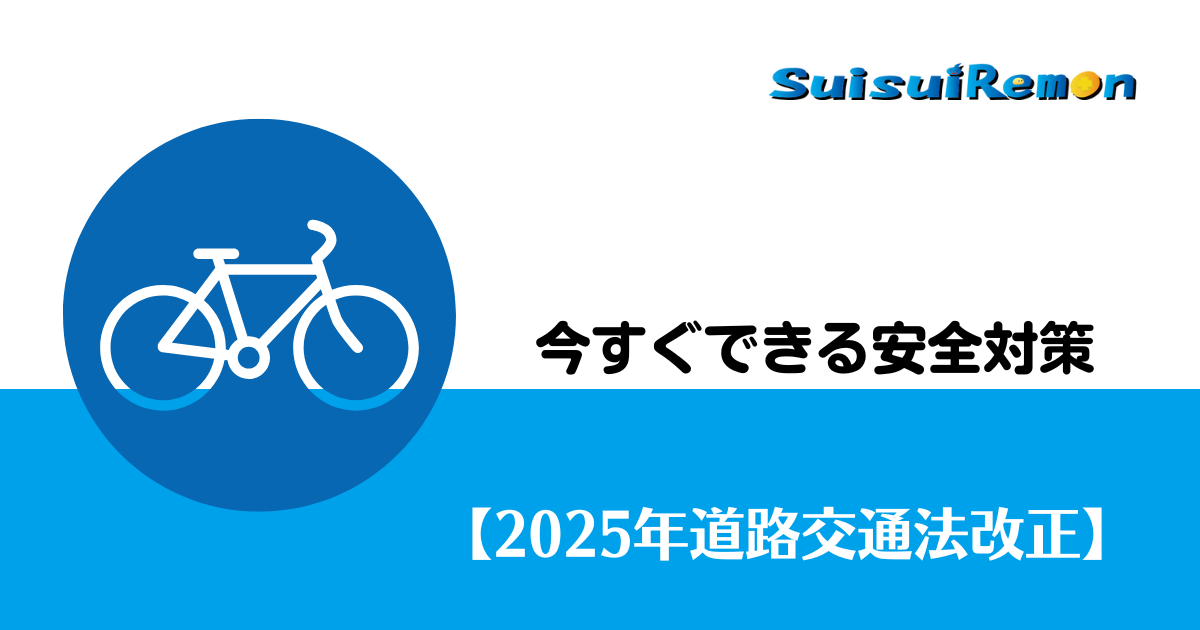【2025年道路交通法改正】事業所が取るべき安全対策とは?訪問介護・看護の“自転車ルール整備術”
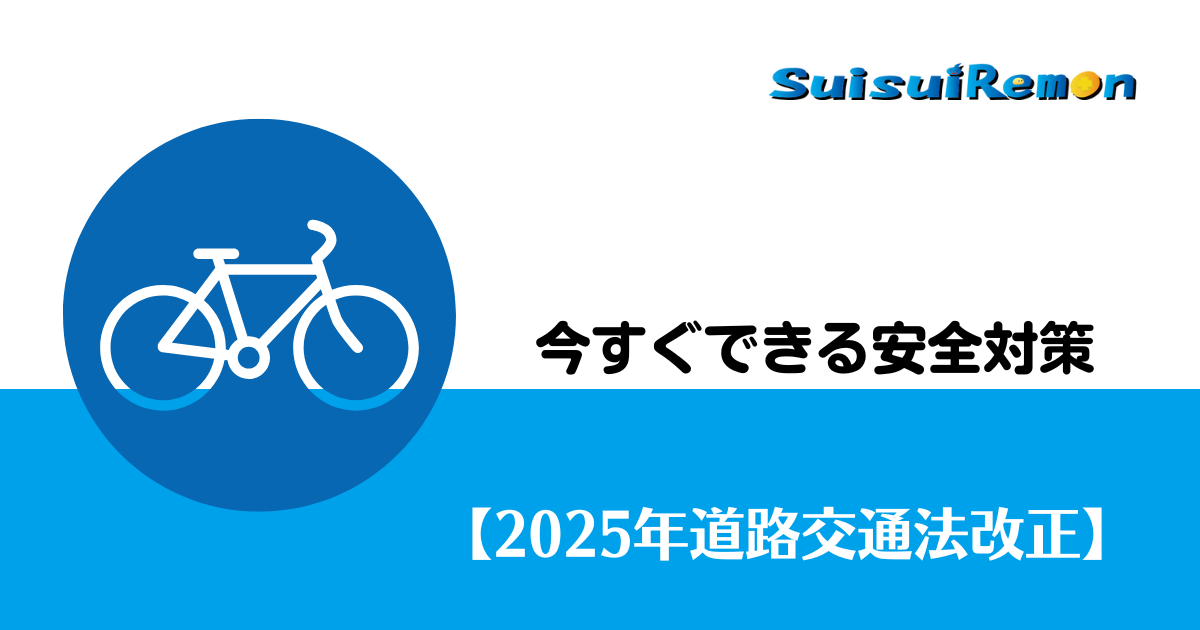
安全対策は「形だけ」で終わらせない
2025年の道路交通法改正により、訪問介護・訪問看護での自転車利用は「個人の意識」ではなく組織の責任として問われるようになります。
「【2025年道路交通法改正】訪問介護・訪問看護での自転車事故と事業者責任とは」で紹介したとおり、業務中の事故は事業者にも法的責任が及ぶ可能性があります。
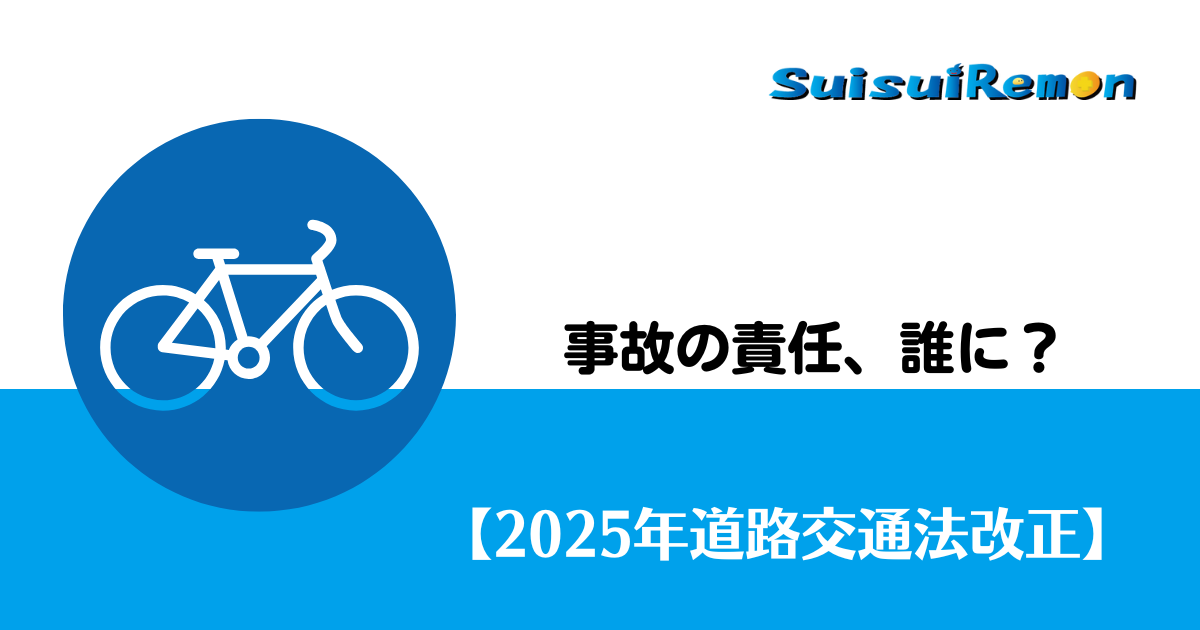
つまり、「気をつけてね」では通用しない時代です。
経営者として求められるのは、“事故を起こさない仕組み”をつくること。
ここでは、すぐに取り組める現場の安全対策とルール整備の具体例を紹介します。
まずは現状把握から。リスクの「見える化」
安全対策の第一歩は、現場の現状を把握することです。
次のチェック項目を確認してみましょう。
- 自転車利用職員の人数、移動距離、利用頻度を把握しているか
- 使用している自転車の種類(私物・会社支給)を区別できているか
- ヘルメット着用率はどの程度か
- 保険加入状況を管理しているか
これらを一覧化することで、どの項目にリスクが潜んでいるかが明確になります。
可能であれば、**「安全管理台帳」**としてExcelやGoogleスプレッドシートで一元管理すると、監査時にも説明しやすくなります。
社内ルールの整備:誰もが守れる“シンプルな基準”に
安全対策は、複雑な規定よりも全員が理解できる運用ルールが効果的です。
以下は実際の事業所で導入が進む代表的なルール例です。
ヘルメット・反射材着用の義務化
- 「業務中は必ずヘルメットを着用」
- 「夜間は反射ベスト・ライトを使用」
- 「ヘルメット未着用での訪問は禁止」と明文化
自転車点検の記録ルール
- 毎月1回、ブレーキ・タイヤ・ライトを点検
- 点検チェックリストを印刷して保管(職員名入り)
- 故障時は使用禁止+管理者報告ルートを明記
悪天候時・夜間時の訪問基準
- 台風・大雨警報時は原則中止または自動車・徒歩に変更
- 18時以降の訪問は原則ライト2灯必須
通勤・業務利用の区別を明確に
- 「業務中」は保険適用範囲内に収まるよう明示
- 私用利用は禁止、必要な場合は管理者に申請
これらを**「自転車利用ルールブック」**として配布し、
新入職員研修時にも説明することで安全意識を統一できます。
教育と研修で「安全文化」を根づかせる
制度を整えても、職員が理解しなければ意味がありません。
「知っている」から「守る」へ変えるためには、教育と継続的な研修が欠かせません。
実施例
- 年1回以上の「交通安全研修」を実施(外部講師 or 警察署協力)
- 事故発生時の「報告・初動対応マニュアル」を共有
- 実際のヒヤリ・ハット事例を共有して再発防止策を話し合う
また、安全運転を評価に反映する仕組み(例:無事故表彰、ポイント制度など)を導入すると、
職員のモチベーション向上にもつながります。
保険・契約の見直しは“経営リスク対策”
自転車事故は「頻度は低いが一度で致命的」なリスクです。
万が一の備えとして、契約内容を以下の3点で確認しましょう。
- 業務中も補償対象になっているか
- 対人・対物の賠償限度額が十分か(目安1億円以上)
- レンタル車両・職員私物も対象に含まれているか
また、職員が私物の自転車を使う場合は、利用申請書+保険証明の提出を求めておくと安全です。
この手続きを行うことで、事業者として「安全配慮義務を果たしている」と示すことができます。
“安全=信頼”をブランド価値に変える
訪問介護・訪問看護は、利用者の命と生活を支える現場です。
その現場において、スタッフの安全を守ることは利用者の安心を守ることでもあります。
ヘルメット着用や点検の徹底は、単なる義務ではなく、
「この事業所はしっかりしている」という社会的信頼の証になります。
安全対策を「コスト」ではなく「ブランド投資」として位置づけ、
社内外に積極的に発信していきましょう。